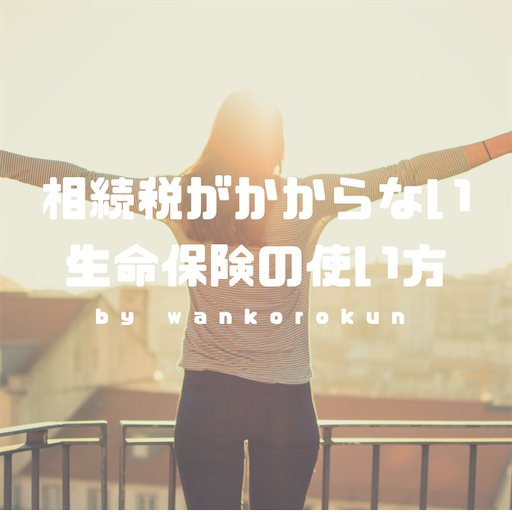
今回も税金のお話。
多くの人が入っている生命保険を使って相続税を節税できる方法を紹介します。
別の記事で紹介したのは、法定相続人1人あたりの非課税枠500万円を上手く利用しましょう、という話でした。
今回は少し別の視点から紹介したいと思います。
生命保険は相続税の課税対象?
生命保険は、本来、受取人固有の財産と言われます。
つまり、被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人となっている場合、厳密にはその生命保険は相続財産ではありません(民法上)。
わかりやすく言い換えると、
亡くなった人が契約した「自分が亡くなった時に妻や子どもに下りる生命保険」は、相続財産ではない、ということです。
一方で、相続税の計算上は、生命保険というお金を相続開始(死亡)に伴い受け取っているわけですからそのお金は「みなし相続財産」として相続財産に含められます。
では、その受け取った生命保険金に対して、まるまる相続税が課税されるのか?というとそうではありません。
この点は、別の記事でも非課税枠があることを紹介しました。
【関連記事】
被相続人に生命保険金がかけられている場合、非課税枠で節税可能。 - CPA Meister
【相続税】相続放棄をしても基礎控除額は変わらない。生命保険金や退職金の非課税枠も同様。 - CPA Meister
法定相続人1人あたり500万円までの生命保険に関する非課税枠があります。
つまり、法定相続人が3人いれば1,500万円までは税金がかからずに生命保険金を相続できることになります。
これは多くの人が思いつく節税方法です。
この保険と「生前贈与」を組み合わせることでより効果的な活用ができる場合がありますので紹介します。
ステップ① 暦年贈与の非課税枠で子や孫に生前贈与を行う
まずは、暦年贈与の非課税枠の範囲内で子や孫にお金を贈与します。
暦年贈与の非課税枠は年間110万円ですから、1年間に無税で贈与を受けることができる110万円までにしておきましょう。
ステップ② 贈与を受けた人が自ら生命保険を契約する
贈与を受けた子や孫は、そのお金を使って「自ら」契約者となって生命保険を契約します。
その際、贈与を受けた人自身が契約者・受取人となり、生命保険を契約することがポイントとなります。
具体的には、仮に夫が亡くなった場合には以下のような保険契約になり保険金が下りるイメージです。
被相続人:夫
保険契約者:子(又は孫)※贈与を受けた人
被保険者:夫
受取人:子(又は孫)
この場合、夫が亡くなった場合に、子どもは死亡保険金を受け取れることになりますが、この保険金には相続税が課税されません。
(ただし、一時所得としての所得税が課税されます。財産規模によっては、一時所得課税の方が負担税額が相当有利になることがあります)
このスキームの注意点
このスキームの注意点として、まず、贈与契約書を作成しておくことです。
贈与契約を作成しておくことで、「贈与」という民法上の契約を成立させることになります。
お金を贈与ではなく、「預けただけ」と税務署に指摘されないよう、契約書はしっかりと作成しておきましょう。
次に、贈与でもらったお金で「もらった人が直接」保険を契約することです。
そうすることで、自身が名実ともに生命保険の契約者となりますので、「名義財産」として相続財産に計上する必要がなくなります。
※名義財産:名義は他人名義だが、実質的に被相続人が負担したもの。相続税の計算上、財産に加算される。
最後に、受け取った保険料には一時所得(所得税)が課税されることになります。
相続税に関する死亡保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)を超えている場合には、一時所得課税とした方が税負担が大きく減少する場合がありますので、節税対策になります。
※詳しくは、税理士に相談ください。
僕も税理士ですので、必要であればお問い合わせフォームよりご連絡頂けましたらご相談を承ります。
所得税の一時所得課税の場合、特別控除枠が50万円あるのと同時に、所得の2分の1相当額に対して総合課税となります。
保険による節税を考えている方はこの方法を検討してみてはいかがでしょうか?